「ヨガ」というと、様々なポーズが思いつきませんか?
もちろんポーズをとることは大切ですが、ポーズを練習する上でヨガ哲学を知っていると、よりヨガの本質を感じることができます。
今回はヨガ哲学の基本的な教えである八支則についてご紹介します。
ヨガの語源
紀元後500年頃、パタンジャリが説いた『ヨーガ・スートラ』という聖典では、「心の作用を止滅することがヨーガである」と定義されています。
この『ヨーガ・スートラ』は、心の科学としてヨガを体系的にまとめた最も古い文献です。
スートラとは「糸」を意味しており、195の短い言葉を糸のように連ねられています。
以下の4つの章から構成されています。
第一章 ヨガの目的から実践方法など概要・定義について
第二章 日常生活での物事の考え方、行動、瞑想のための姿勢、呼吸調整について
第三章 ヨガを深めることで生まれる知恵や能力について
第四章 ヨガの哲学や心理学などの補足
ヨガインストラクターやヨガ愛好家など、ヨガを実践する人は読んでおきたい一冊です。

![]()
『ヨーガ・スートラ』に書かれているヨガは、瞑想や坐法を中心とした静的なヨガのことになります。
この静的なヨガのことを「ラージャ・ヨーガ」といい、「ラージャ・ヨガ」を進化させていったものが、現在の「ハタ・ヨガ」になります。
ヨガの語源
ヨガとは、サンスクリット語で「ユジュ(yuj)=結ぶ、繋ぐ」が語源と言われています。
馬車をひく馬の首に軛(くびき)を繋ぐという意味があり、『ヨーガ・スートラ』の中では以下のように例えられています。
・馬車…肉体
・御者…知性や判断を下す理性
・乗客…真我(魂)
・手綱…情報の授受を伝達する意識
・馬…感覚器官
優れた御者は馬をきちんとコントロールできますが、御者のコントロール次第では馬が暴走してコントロールできなくなってしまう可能性があります。
御者が振り落とされて馬車が壊れてしまったり、目的地へ到着することも難しい場合も考えられますよね…。
私たちの感情も同様です。
感情の波に振り回されていると、人生の目的を見失ってしまったり、心や身体が病気になってしまいます。
つまり、御者は馬の首に繋いでいる手綱で、馬(感覚器官)を上手くコントロールする技術が必要なのです。
そして、乗客である真我(魂)の望む方向に導いていくことが理想的な人生なのです。
私たちの日常では、心と身体がバラバラに離れています。
例えば、テレビやスマホを見ながらご飯を食べたり。
何か作業しながら、別のことを考えたり。
肉体がしていることと、心が在る場所が違うんですよね。
常に様々な情報と刺激で溢れていますが、その全てを受け取ろうとすると心が疲れてしまいます。
この色々な方向に飛び散っている意識を一つにまとめて心と身体を繋ぐのがヨガなのです。
自分の心をコントロールすることができると、外の情報や障害に振り回されることなく、いつでも穏やかな心でいることができます。
心と身体が繋がったときにはじめて、私たちはその瞬間をフルで感じて味わうことができるのです。
八支則
ヨガの教えには、八支則(はっしそく)という8つの段階・行法があります。
聖者パタンジャリが説いた「ヨーガ・スートラ」という聖典の中に出てくる、ヨガ哲学の基本的な教えです。
①Yama(ヤマ)
他人や物に対して日常の中でおこなってはいけないこと。道徳的基本。
Ahimsa(アヒンサ)
非暴力。考え、言葉、身体を使った行いで、人や自然を傷つけないこと。
Satya(サティヤ)
嘘をつかないこと。人や自然を傷つけないように、いつも考えと言葉に一貫性を持つこと。
Asteya(アスティーヤ)
盗まない。他の人の所属するものを欲しがったり、奪ったりしない。
Brahmacharya(ブラフマチャリヤ)
禁欲。一時的な快楽に更けることを制御する。
Aparigraha(アパリグラハ)
貪欲さのないこと。自分の根っこの問題を注意深く見て、貪欲に陥らない。
②Niyama(ニヤマ)
日常の中で推奨されること。自分に対して守るべき行動。精神的に守ること。
Shaucha(シャウチャ)
純潔。考え、身体、環境を清らかに保つ。
Santosha(サントーシャ)
満足感を感じる。最低限必要なものを持つシンプルな満ち足りた生活を楽しむ、今ある環境に感謝する。
Tapas(タパス)
鍛錬すること。辛く苦しい状況でも、客観的な理解を持って耐える。
Swadhyaya(スワディヤーヤ)
継続的な勉強。経典や自分自身に対する学びを深め、精神向上を行う。
Ishvarapranidhana(イーシュワラプラニダーナ)
神への祈念。自分の行動と意思を、最大限に全世界に奉仕すること。
③Asana(アサナ)
ヨガのポーズ。
いわゆる、一般的に知られているヨガ。
アサナと共に意識を体の内側に向けていく。瞑想への準備。
④Pranayama(プラーナヤーマ)
呼吸と身体・心を繋げることに意識を向けていく。
意識的な呼吸を行うことで、自分自身に活力を与える。
⑤Pratyahara(プラティヤハーラ)
感覚の制御。
感覚をコントロールする。
外からの注意を五感から引き離して内観し、安定した精神状態を保つ。
⑥Dharana(ダーラナ)
周りが気にならない、集中している様子。
意識を安定、一点に留め動かさない。
⑦Dhyana(ディヤナ)
瞑想状態。
深い静かな精神状態で落ち着いている。
⑧Samadi(サマーディ)
深い瞑想と融合しておこる、悟りの境地 。最高次の超意識状態。
実践してみよう
ヨガ哲学を知らなくてもヨガはできます。
ですが、この八支則、特に「ヤマ」「ニヤマ」には日常生活の指針が書かれているので、私たちが生きる上でのヒントやエッセンスがたくさん詰まっています。
私も少しずつ日常に取り入れるようにしてから、ヨガマットの外でもヨガを感じられるようになりました。
いきなり全てを実行するのは結構ハードルが高いですが、まずはできることからはじめてみてください♪
まとめ
ヨガ哲学を学んで7年ほど経ちますが、最近になってやっと腑に落ちたことがたくさんあります。
まだまだ勉強中ですが、理解度が少しでも深まると、本来持っている自分の可能性に光が当たり、迷うことなく自分の道を進めるような、そんな気がします。
一生かけて、このヨガ哲学を学んで自分の人生で体験していきたいと思います。
ヨガ哲学が学べるスクール↓





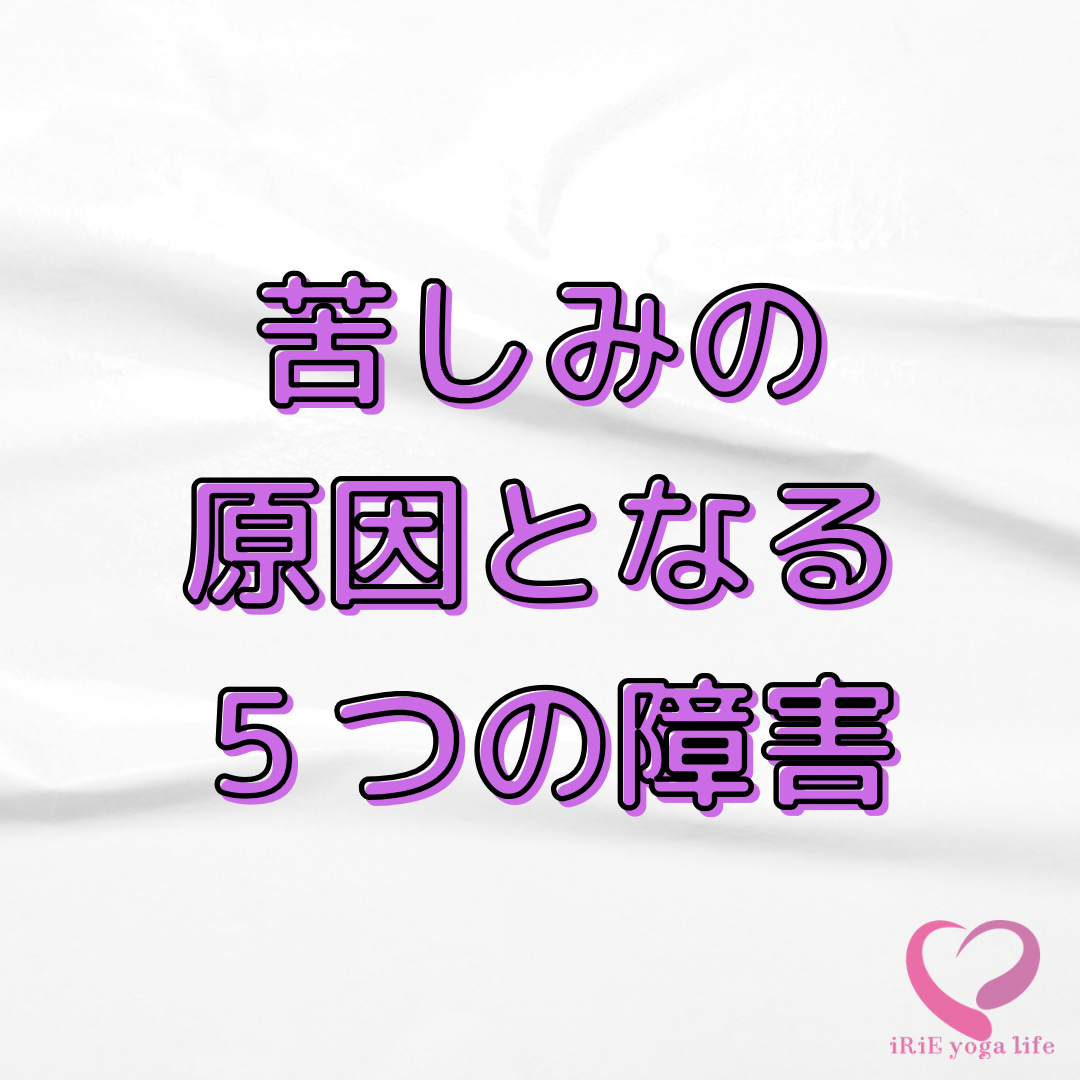
コメント